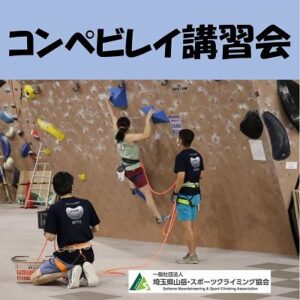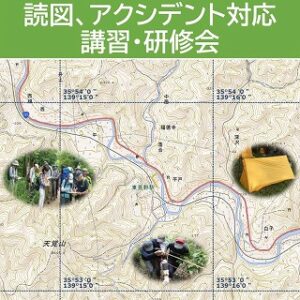令和7年度 指導委員会総会及びコーチ資格更新研修会6/22 報告
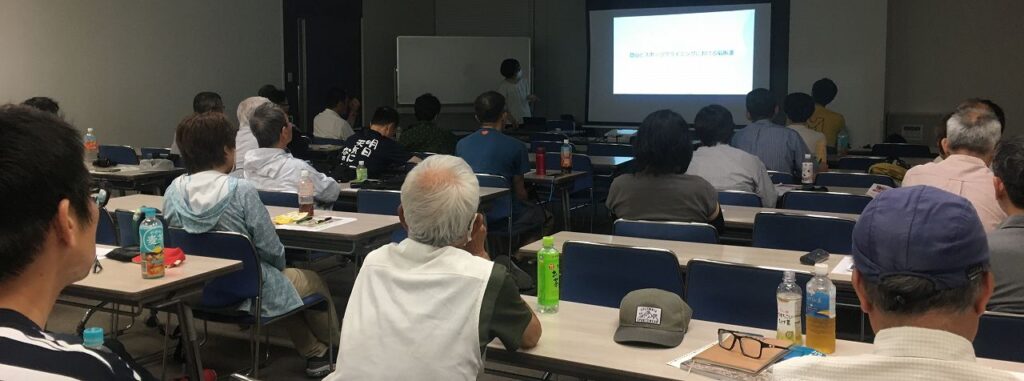
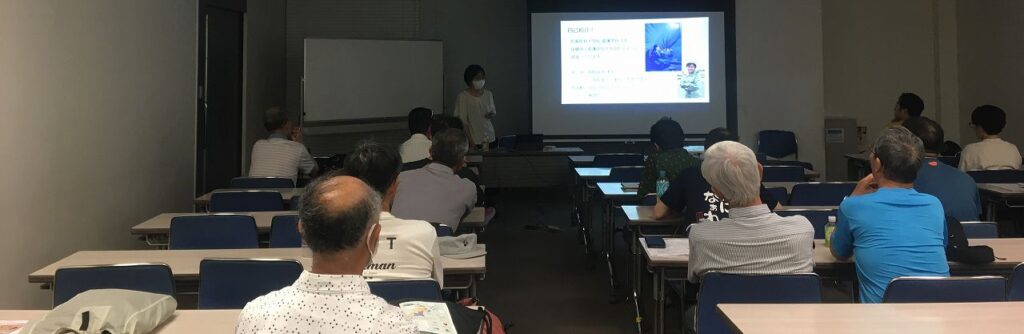
令和7年度 指導委員会総会及びコーチ資格更新研修会6/22 報告
開催日時:2025年6月22日(日)18:10~ 21:00
会場:浦和コミュニティセンター第14集会室
参加者:30名(山岳コーチ1/16名・山岳コーチ2/13名・クライミングコーチ1/1名)
講師:伊藤 正孝 先生(防衛医科大学教授・SMSCA理事・医科学委員会委員長)
講師:竹花 奈々(防衛医科大校 看護学科4年)
◆指導委員会総会 JMSCA全国指導委員長会議報告 18:10~ 担当:矢田
・2024年度事業報告・決算報告及び2025年度事業計画・予算案の報告を行い、承認されました。
・2025年5月31日・6月1日に行われた、JMSCA全国指導委員長会議/スポーツクライミング代表者連絡会議について報告を行いました。
・SMSCA登山学校・講師登録アンケートについて依頼
資料を配布し、調査概要の説明を行いました。
講師をお願いする事になる、指導員資格者の得意とする分野・活動等をネットにて調査
・SMSCA70周年事業「親子・友人とのクライミング体験会」のスタッフを募集
7月27日(日) 加須市民体育館 ビレイヤー10名
◆研修1 19:00~ 担当:矢田
・JMSCA公認夏山リーダーの概要と埼玉県指導委員会の取り組みについて
・UIAA公認上級夏山リーダーの概要
・共済会について
★JMSCA公認夏山リーダーついて(JMSCA HP)
https://www.jma-sangaku.or.jp/sangaku/leader/
受講条件
JMSCA公認夏山リーダーは、講習会のレベルを保つためにある程度の経験者を対象とする
受講条件 受講時の年齢:満18歳以上 登山経験:2年以上20回以上の登山経験
★UIAA公認上級夏山リーダーについて
上級夏山リーダーは、国際山岳連盟UIAAより、教育内容と教育法、そのシステムを支える指導組織に関して審査があり、2022年12月に承認さました。
メンバーに登山知識・経験が浅く、危険の予知、回避能力が十分でない人々をサポートする「引率型リーダー」の養成を目指します。
受講条件
年令19歳以上で、JMSCA公認夏山リーダー(基礎編)の資格保有者かJSPO公認山岳コーチ1以上の資格保有者
◆研修2-前半 19:30~ 講師:伊藤 正孝 先生
動画配信:「登山とスポーツクライミングにおける熱中症とその予防について」
内容
- 熱中症とは?
2.WBGT(暑さ指数)とは?
3 熱中症の症状と予防 - 熱中症アンバサダーについて
熱中症とは、暑い環境に体がうまく適応できず、正常の体温が維持できなくなるとともに、体内の塩分・水分のバランスが崩れた状態。
1912年(明治45年)7月 ストックホルム五輪でのマラソン競技を事例に挙げ説明
WBGT(暑さ指数)は、熱中症の危険度を評価するために用いられる指標で、気温、湿度、日射・輻射熱を総合的に考慮して算出される。WBGT値は、日常生活や運動、作業時の熱中症予防のための目安として活用されている。
熱中症の予防と手当について
予防策としては、こまめな水分・塩分補給、適切な服装、休憩、暑さに慣れるための準備などが重要
手当としては、涼しい場所への移動、衣類の緩め、冷却、水分・塩分補給が基本
意識がない場合は、無理に水分を飲ませず、速やかに医療機関を受診する
熱中症アンバサダーについて
受講者は、私を入れて2名のみ。有益な制度なので、参加者へ受講を勧めた。
◆研修2-前半 19:30~ 講師:竹花 奈々
「登山とクライミングにおける脳しんとう」
脳しんとうを、耐震構造のせん断力イラストを使ってわかりやすく解説したり、参加者で「バランステスト」を体験するなど、とても工夫された楽しい講習でした。
脳しんとうとは
頭や体に外から衝撃をうけることで、頭蓋骨の中で脳が揺さぶられ、脳の中の神経繊維が切れたり伸びたり捻れたりする,脳の怪我です。
・脳しんとうは頭や体をぶつけた時に起こりうる
・脳しんとうの可能性がある場合は,活動を中止する
・10の徴候とバランステストで確認
・意識がない,二重に見える,手足の脱力は救急車
・症状が長く続くなら,脳外科を受診
★SMCSA脳しんとう予防啓発プロジェクトについて
SCにおいて脳しんとうが生じうる場面は多く存在するが、日本山岳・スポーツクライミング協会(JMSCA)における脳しんとうに関するガイドラインはなく、HP等での脳しんとうに関する一般向けの啓発も十分にはなされていない。→若年者の脳しんとうの後遺症はその後に大きく関わることからも、特に対策が必要
★特別講座
「山岳会に所属する高齢者の登山継続と健康に関するアンケート調査」結果報告
約6割の人が、何らかの疾患を抱えながら登山を継続
疾患をもつことが、登山をやめることと直接関連しない場合が多い。
疾患を抱えたとしても、適切な健康管理がなされていれば、高齢になっても登山活動を続けることが可能である
高齢者の登山継続を妨げる要因として、疾患の有無よりも加齢に伴う体力・技術レベルの低下が大きく影響していることが示唆された
※飛行機の延着で、竹花 奈々さんの会場到着が遅れた為、順番を入れ替えて実施
報告 指導委員長 矢田 実